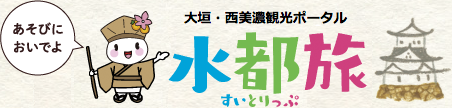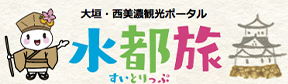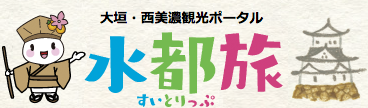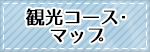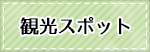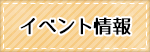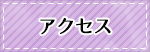美濃路は、中山道垂井宿(岐阜県不破郡垂井町)と東海道宮(熱田)宿(愛知県名古屋市)とを結ぶ全長約58kmに及ぶ街道でした。中山道の木曽谷、東海道の鈴鹿峠や七里の渡しといった難所を避けることができるため、多くの人がこのんで通行したほか、大名行列をはじめ、朝鮮通信使、琉球使節、お茶壷道中などにも利用される重要な街道でした。
また、関ケ原合戦の後、徳川家康が凱旋しためでたい道であったことから「御吉例街道」と呼ばれています。

-
垂井宿は中山道第57番目の宿で、中山道と東海道を結ぶ美濃路の分岐点となる宿場です。中山道の合流する手前には美濃路沿いで唯一の松並木が残り、宿の西日守には国指定史跡の一里塚があり、当時の街道の面影をうかがうことができます。
-
戸田氏10万石の城下町であり、美濃路の宿場町でもありました。桑名へと続く水門川を利用した舟運の拠点である船町港があり、水・陸運ともにさかえ、にぎわいました。本陣1軒(竹島町)、脇本陣1軒(本町)、問屋場(伝馬町のちに竹島町)があり、松尾芭蕉が紀行文学『奥の細道』のむすびの地として訪れたことで知られています。
-
豊臣秀吉の出世の足がかりとなった墨俣は、鎌倉街道が通るなど古くから交通の要衝として知られています。墨俣の東を流れる墨俣川(長良川)には渡船場があり、享保14年(1729)ベトナムから来た象が、長崎から江戸へ下る際、ここから船で渡りました。
-
起川(木曽川)沿いに3ヶ所の渡し口をもつ渡船場の宿場としてにぎわいをみせました。将軍家、朝鮮通信使などの通行の際に起川に架けられた船橋は、270隻以上もの船をつなげたもので、国内でも最大級の規模でした。
-
萩原宿は、天保14年(1843)の資料(「美濃路宿村大概帳」)によると、人口、家数ともに美濃路の中では最も小さい宿場で、宿役は萩原、西之川、串作の3村が勤めました。
-
稲葉宿は稲葉村と小沢村によって構成された宿場でした。本陣、脇本陣のほか問屋場が3か所あり、東問屋場(小沢村)を原氏、中問屋場(稲葉村東町)を伊東氏が勤め、西問屋場(稲葉村西町)は原氏と伊東氏の両氏が、1問屋場2日交代で勤めたといいます。
-
慶長7年(1602)に清洲城下に宿場が設けられましたが、慶長15年(1610)の名古屋城築城により荒廃した後、元和2年(1616)に美濃路の宿として再び整備されました。その後火災で宿場は焼失し、これを機に宿場を五条橋近くの神明町に移しました。
-
名古屋宿は尾張藩の城下町で、通常の宿場とは異なり、本陣や脇本陣はなく、旅籠屋も宿場内にはありませんでした。そのため、諸大名の宿泊はなく、名古屋宿は通過するのみでした。一般の旅人は、宿場に近い玉屋町にあった旅籠屋を利用しました。
-
宮宿は、熱田神宮の門前に位置するため宮の宿、熱田宿とも呼ばれ古くから栄えました。門前町であるとともに、桑名宿への七里の海上渡し場であり、佐屋路(さやじ)・美濃路の分岐点でもありました。
美濃路を歩きながら大垣をめぐる
大垣市内の宿場(大垣宿、墨俣宿)周辺のおすすめスポットを紹介します



中山道と東海道を結ぶ美濃路街道の宿場町として栄えた大垣宿は、本陣、脇本陣、問屋場、旅籠屋、商家などが軒を連ねており、本陣は、大名や公家などの宿泊施設や文化人の交流施設として利用されていました。
現在は、大垣宿本陣跡附明治天皇行在所跡として大垣市の史跡に指定されており、週末には一般公開されています。
| 所在地 | 大垣市竹島町39 |
|---|---|
| 定休日 | 土日祝のみ開館、冬期閉館、 その他不定期閉館 |
| 電話番号 | 0584-47-8597 (大垣市商工観光課) |



大河ドラマ「麒麟がくる」でもその名と姿が登場した大垣城は、交通の要所であり、尾張との国境近くに位置しする重要拠点であったため信長の父・織田信秀と斎藤道三の間で激しい奪い合いになりました。
昭和20年、惜しくも戦災で焼失したものの、かつて城を守っていた外堀は水門川としてその姿を残し、復興された天守は大垣市のシンボルとして親しまれています。
| 所在地 | 大垣市郭町2-52 |
|---|---|
| 定休日 | 火曜、祝日の翌日 |
| 電話番号 | 0584-74-7875 |



創業260年を超える老舗「御菓子つちや」の本店として、明治時代に建てられました。
立派なうだつ風の防火壁が設置されており、歴史的な価値も高いことから、大垣市の景観遺産に指定されています。
岐阜県産の堂上蜂屋柿を使用した「柿羊羹」は、大垣名物として多くの人に親しまれています。
| 所在地 | 大垣市俵町39 |
|---|---|
| 定休日 | 元日 |
| 電話番号 | 0584-78-2111 |



水門川の船町港は、江戸時代に大垣藩によって整備されて以降、西濃地域の人・物資・文化の交流拠点として人々の生活を支えてきました。
現在は、「おくのほそ道の風景地 大垣船町川湊」として国指定の名勝となっており、多くの観光客が訪れる名所となっています。
| 所在地 | 大垣市船町2丁目 |
|---|---|
| 定休日 | なし |
| 電話番号 | 0584-77-1535(大垣観光協会) |



大垣の歴史・文化を発信する観光施設。
松尾芭蕉や「奥の細道」に関する資料・映像を紹介する「芭蕉館」、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した5人の先賢の偉業を紹介する「先賢館」、観光情報などを紹介する「観光・交流館」のほか、大垣のお土産品を多数取り揃えた「お休み処 芭蕉庵」があります。
| 所在地 | 大垣市船町2-26-1 |
|---|---|
| 定休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 電話番号 | 0584-84-8430 |



明治時代に建てられた木造・土蔵造りの酒蔵は、戦災による焼失を免れ、今も稼働している貴重な産業遺構として、大垣市景観遺産に指定されています。
代表的な銘柄である純米にごり酒「白川郷」や、特別本醸造「バロン鉄心」は、手土産や贈答用として親しまれています。
| 所在地 | 大垣市船町4-48 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜、祝日 |
| 電話番号 | 0584-78-2201 |



江戸時代、美濃路の宿場町として栄えた墨俣宿の脇本陣跡。
現在の建物は濃尾震災で倒壊した後に再建されたものですが、かつての宿場町の面影を偲ぶことができます。
| 所在地 | 大垣市墨俣町墨俣115 |
|---|---|
| 定休日 | なし |
| 電話番号 | なし |



大垣市の景観遺産にも指定されている墨俣宿の寺町界隈。その名の通り古くからの寺院が集まり、昔の面影を残しています。
各寺院には文化財が多く、熊谷院 満福寺には豊臣秀吉の書と伝わる寺宝も。(要予約)
早春のころ、境内に鮮やかな白・紅・桃色の枝垂れ梅が咲き乱れる光受寺もまた、寺町の大きなおすすめスポットです。
| 所在地 | 大垣市墨俣町墨俣寺町 |
|---|---|
| 定休日 | なし |
| 電話番号 | なし |



信長の岐阜城攻めに際し、木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)が一夜にして築いたと伝えられる墨俣一夜城。
秀吉が「天下人」となる出発点となったことから「秀吉出世城」とも呼ばれています。
城の周辺には、秀吉が馬印とした「ひょうたん」が随所にありますので、ぜひ探してみてください。
| 所在地 | 大垣市墨俣町墨俣1742-1 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜、祝日の翌日 |
| 電話番号 | 0584-62-3322 |