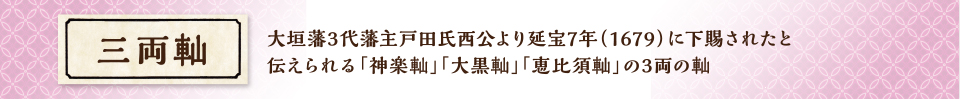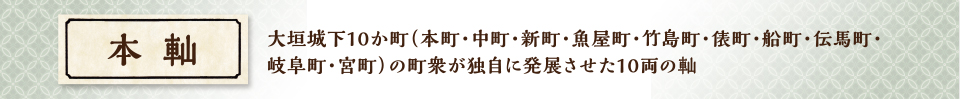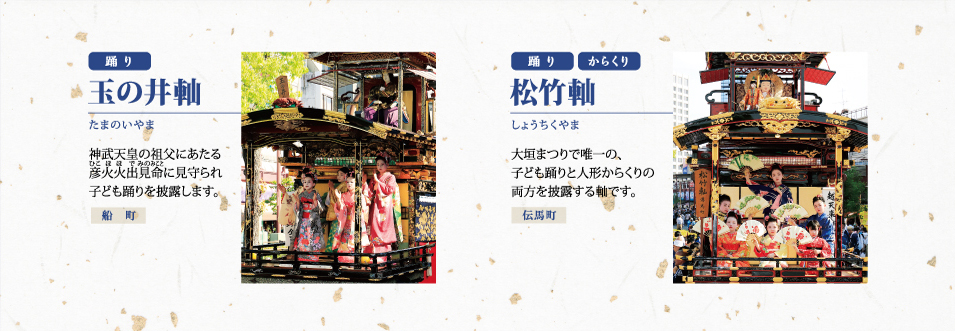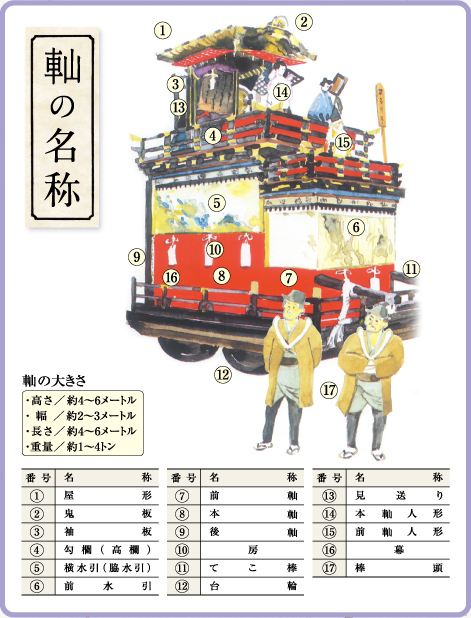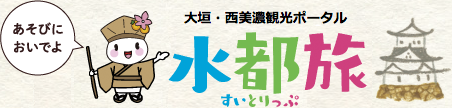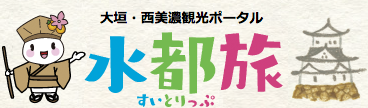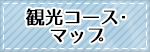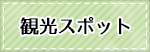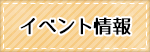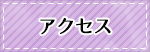| とき | : | 平成30年10月14日(日) 10:00~15:00 |
| ところ | : | 大垣駅通り(元気ハツラツ市会場) |
| 主催 | : | 大垣観光協会 |
| 主管 | : | 大垣祭出軕運営委員会 |
| お問合せ | : | 大垣観光協会 TEL:0584-77-1535 |

- 来年の大垣まつりは
2019年5月11日(土)・12日(日)です。

城下町大垣に初夏の訪れを告げる大垣まつり。大垣まつりは、370年の伝統を誇り、13両の軕が城下町を巡行し、華麗な祭絵巻を繰り広げます。
大垣まつりの軕の起源は、慶安元年(1648)、大垣城下町の総氏神であった八幡宮が十万石初代藩主戸田氏鉄(うじかね)公により再建整備されたおり、城下18郷が喜びを御輿3社の寄付で表し、大垣10か町(本町・中町・新町・魚屋町・竹島町・俵町・船町・伝馬町・岐阜町・宮町)が10両の軕(出しもの)を造って曳き出したのが始まりと伝えられています。
延宝7年(1679)、藩主戸田氏西(うじあき)公から、神楽軕・大黒軕・恵比須軕のいわゆる三両軕を賜り、それを機に10か町は、軕の飾り付けに趣向を凝らしていきました。しかし、濃尾震災や戦火によって多くの軕を失います。その後、修復や復元、購入などにより軕の再建が進められ、平成24年に全13両の軕が勢ぞろいしました。平成27年、東西の祭礼文化と藩主下賜(かし)の軕が残ることが評価され、「大垣祭の軕行事」として国重要無形民俗文化財に指定。さらに平成28年、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
大垣まつりの特徴でもある2.2里(約8.8km)の本楽軕巡行は、東回りと西回りの年次交代で行われております。
大垣まつりの軕の起源は、慶安元年(1648)、大垣城下町の総氏神であった八幡宮が十万石初代藩主戸田氏鉄(うじかね)公により再建整備されたおり、城下18郷が喜びを御輿3社の寄付で表し、大垣10か町(本町・中町・新町・魚屋町・竹島町・俵町・船町・伝馬町・岐阜町・宮町)が10両の軕(出しもの)を造って曳き出したのが始まりと伝えられています。
延宝7年(1679)、藩主戸田氏西(うじあき)公から、神楽軕・大黒軕・恵比須軕のいわゆる三両軕を賜り、それを機に10か町は、軕の飾り付けに趣向を凝らしていきました。しかし、濃尾震災や戦火によって多くの軕を失います。その後、修復や復元、購入などにより軕の再建が進められ、平成24年に全13両の軕が勢ぞろいしました。平成27年、東西の祭礼文化と藩主下賜(かし)の軕が残ることが評価され、「大垣祭の軕行事」として国重要無形民俗文化財に指定。さらに平成28年、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
大垣まつりの特徴でもある2.2里(約8.8km)の本楽軕巡行は、東回りと西回りの年次交代で行われております。