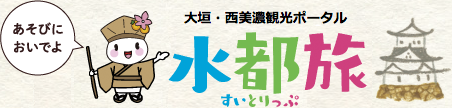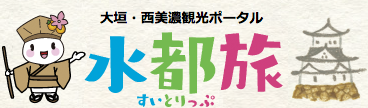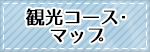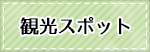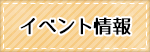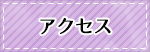明智光秀 生誕の地 多羅城

多羅城は、大垣市上石津多良地区にかつてあったと推察される戦国時代の城館です。関ケ原の戦い以前、この地を所有していた関一政が多羅(良)城を築いたとされ、築城時期は天正年間とも慶長年間とも言われています。
しかし、明智光秀が多良で生誕したとされる史料には、“多羅は進士家の居城”とあるため、関氏以前から多羅城は存在していた可能性があります。慶長5年(1600)、関ケ原の戦いの後、関一政は伊勢国亀山(現亀山市)に移封となり、代わって高木貞利がこの地に転封され旗本となりました。
多羅城の場所等の特定には至っていませんが、推定される場所が複数あります。宮の西高木家陣屋跡や羽ケ原の城ケ平、上多良の城屋敷、松ノ木の城山などが城跡とされる場所で、それぞれの地名に「城」の名が今も残されています。
しかし、明智光秀が多良で生誕したとされる史料には、“多羅は進士家の居城”とあるため、関氏以前から多羅城は存在していた可能性があります。慶長5年(1600)、関ケ原の戦いの後、関一政は伊勢国亀山(現亀山市)に移封となり、代わって高木貞利がこの地に転封され旗本となりました。
多羅城の場所等の特定には至っていませんが、推定される場所が複数あります。宮の西高木家陣屋跡や羽ケ原の城ケ平、上多良の城屋敷、松ノ木の城山などが城跡とされる場所で、それぞれの地名に「城」の名が今も残されています。

明智光秀は、40歳を過ぎ、織田信長の家来となって頭角を現してから初めて歴史の表舞台にその名を残します。
前半生の姿が全くと言っていいほど解明されておらず、どこで生まれ誰の子なのかも定まっていません。
そのため、現在では数少ない史料をもとに、美濃の守護・土岐氏一族の出身とするものが通説となるも、生誕地については諸説あります。
ここ、大垣市上石津町多良地区にかつて存在したとされる多羅(良)城も、生誕の地のひとつに考えられています。
前半生の姿が全くと言っていいほど解明されておらず、どこで生まれ誰の子なのかも定まっていません。
そのため、現在では数少ない史料をもとに、美濃の守護・土岐氏一族の出身とするものが通説となるも、生誕地については諸説あります。
ここ、大垣市上石津町多良地区にかつて存在したとされる多羅(良)城も、生誕の地のひとつに考えられています。


明智光秀は、1528年8月17日石津郡多羅に生、多羅は進士家の居城 母は明智家当主「明智光綱」の妹で、明智家当主光綱に子供が無かったので、養子として明智城に入った。幼かったので、光綱の弟、叔父の兵庫頭光安入道宗寂後見とした。
弘治2年(1556)9月明智城落城後、しばらく浪人し、のち足利義昭公に仕え、その後織田信長に仕えた。天正10年(1582)6月13日夜、小栗栖に於いて死亡。年55歳。
明智光秀の母は、明智家当主「明智光綱(光隆)」の妹で、石津郡多羅を居城としていた進士信周の嫁にきたが、兄に子がなく、自分の次男を兄の養子として渡した。これが後の明智光秀だとされます。
弘治2年(1556)9月明智城落城後、しばらく浪人し、のち足利義昭公に仕え、その後織田信長に仕えた。天正10年(1582)6月13日夜、小栗栖に於いて死亡。年55歳。
明智光秀の母は、明智家当主「明智光綱(光隆)」の妹で、石津郡多羅を居城としていた進士信周の嫁にきたが、兄に子がなく、自分の次男を兄の養子として渡した。これが後の明智光秀だとされます。
光秀は明智光隆と妻との間に生まれ、その出生の地は美濃多羅城。光秀の出生の地は多羅城と書かれています。
 西高木家陣屋跡は、近世陣屋として良好に残る石垣・墓所・地下遺構・建造物などの現地遺構に加え、絵図類を含む膨大な量の古文書群が残り、近世幕藩領主の姿を豊富な資料によって現在に伝える全国的にも貴重な遺跡として、平成26年国の史跡に指定されています。
西高木家陣屋跡は、近世陣屋として良好に残る石垣・墓所・地下遺構・建造物などの現地遺構に加え、絵図類を含む膨大な量の古文書群が残り、近世幕藩領主の姿を豊富な資料によって現在に伝える全国的にも貴重な遺跡として、平成26年国の史跡に指定されています。高木家は、大和高木村の出で、伊勢を経て、享禄元年(1528)に美濃に移ったとされます。齋藤道三・織田信長に仕え、美濃南部の駒野・今尾を拠点としました。一時甲斐に赴きましたが、関ケ原の戦いの功により、慶長6年(1601)に美濃の時・多良(現大垣市上石津町時・多良地区)の地を拝領し入郷、西高木家・東高木家・北高木家三家それぞれで陣屋を構えました。高木家の石高は三家で4,300石でしたが、交代寄合として大名の格式を許され特別な役儀を負いました。まずひとつに、時・多良地区は美濃と近江・伊勢との国境で、高木家はその警固にあたりました。また、木曽三川の治水行政にあたる川通御用としても重要な役目を負い、宝永2年(1705)より幕末まで、水行奉行として美濃・伊勢・尾張の諸河川の管理にあたりました。江戸時代中期、木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)を分流した難工事・宝暦治水にも工事監督責任者のひとりとして深く関わりました。
|
[バスご利用] ・JR関ケ原駅から名阪近鉄バス関ケ原時線「宮」下車、徒歩2分 |
|
[高速道路ご利用] ・名神高速道路関ヶ原ICから 国道365号線で25分 ・名神高速道路養老スマートICから 県道227号線・国道365号線で20分 ・東名阪自動車道桑名ICから 国道421号線・365号線で1時間15分 |

国史跡の西高木家陣屋跡に建つ資料館。上石津で出土した石器、民俗資料、動植物の標本を展示するほか、「島津の退き口」の紹介もしています。
| 所在地 | : | 大垣市上石津町宮237-1 |
|---|---|---|
| 入場料 | : | 大人100円、18歳未満無料 |
| 時間 | : | 9:30~17:00(入場16:30まで) |
| 休日 | : | 火曜日、祝日の翌日、年末年始 |
| 電話 | : | 0584-45-3639 |